プロジェクト
レポート
浄土真宗高田派本山専修寺および一身田寺内町において、文化遺産防災の現地視察を行った。まず、専修寺で寺院や宗派の概要と建物の防災施設についての説明を受けた後、建物の見学をした。その後、地元のボンティアの案内によって、寺内町の濠、町並みなどの見学を行った。最近になって新しい家屋が増えたものの、一身田寺内町には町を取り囲む濠や歴史ある街並みが残っている。その後、寺内町にある「一身田寺内町の館」会議室にて、地元の龍谷大学名誉教授の平野令三先生、三重大学名誉教授の水越允治先生から補足的な説明を受けた。専修寺と寺内町の関わり、町並み保存、文化遺産防災に関する興味深い課題を探ることができた。
 専修寺
専修寺 一身田寺内町
一身田寺内町12月13日午後1時30分から5時まで、創思館カンファレンスルームにて、「文化遺産―伝統を災害から守る―」をテーマにシンポジウムが開催された。(財)奈良屋記念杉本家保存会事務局長の杉本節子氏から「京町家『杉本家住宅』の保存活動について」、(株)老松代表取締役社長の太田達氏から「京都花街の形成と災害」、NHKエンタープライズエグゼクティブプロデューサーの大井徳三氏から「文化財保護とマスメディア」、(財)祇園祭山鉾連合会副理事長の吉田孝次郎氏から「山鉾と天明の大火。町衆の知恵」と題する4件の発表があった。約100名の参加者は、京都の文化に造詣の深い発表者の興味深い話に聴衆は聞き入っていた。
今年度末で、学術フロンティア推進事業「文化遺産と芸術作品を自然災害から防御するための学理の構築」プロジェクトが終了するため、その研究メンバーによる成果の発表会が当日の午前中に創思館の3会場で行われ、22件の発表があった。ここでは熱心な議論が交わされた。また、その成果を歴史都市防災研究センターにA0のパネルにして展示している(しばらくの間、継続して展示するので、是非御覧いただきたい)が、シンポジウムの終了後、研究メンバーによるパネルの説明・解説も行われ、シンポジウムの参加者が熱心に話を聞く姿が見られた。

.jpg)
「第3回夏休みにみんなで作る地域の安全安心マップコンテスト」表彰式(2009.10.31)
歴史都市防災研究センターカンファレンスホールにおいて「第3回夏休みにみんなで作る地域の安全安心マップコンテスト」の表彰式が行われた。土岐センター長からの挨拶の後、審査委員の吉越副センター長から審査の講評が行われた。その後、最優秀賞・優秀賞・入選・佳作・努力賞の表彰状と副賞が作成した小学生に手渡された。受賞者からは、作成した地図で見て欲しいところなどの簡単な説明があった。今年の安全安心マップの特徴は、詳しい情報や写真などを含めたものが多く、年々質が向上してきていることが伺える。
この安全安心マップは、表彰式の日から11月末まで、日曜日・祝日を除く毎日(土曜日も)歴史都市防災研究センターの展示室にて展示されている。


学術フロンティアの今年度事業の一環として、鹿苑寺(金閣寺)の防災システムの見学会を開催した。小雨の降る中ではあったが、鹿苑寺執事の緒方氏より、最新の防災施設の説明と考え方について詳細なお話をいただいた。参加者は30名を越え、防災施設では多くの質問があった。今回の経験では、文化遺産防災を研究する上で貴重なヒントを得ることができた。


創思館カンファレンスルームにおいて、表題の講演会を開催した。これは、4月8日~5月10日に歴史都市防災研究センターにおいて開催されている「地図を通して見る関東大震災」展を記念して行われた講演会で、鹿島建設小堀研究室プリンシプル・リサーチャーの武村雅之氏、東京大学大学院准教授の鈴木淳氏、防災アンド都市づくり計画室代表・首都大学東京客員教授の吉川仁氏の3名によって、最近の研究の成果を紹介されたものであった。終了後、講演された3名ほか、展示の企画担当者による展示案内があった。講演会・展示案内ともに熱心な多くの参加者によって、質疑が交わされた。


防災教育チャレンジプラン実行委員会主催「2008年度防災教育チャレンジプラン」で、防災教育に関する優秀な実践団体として、第2回地域の安全安心マップコンテストについて報告がされました。
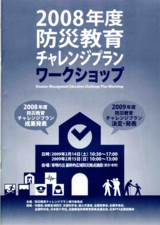
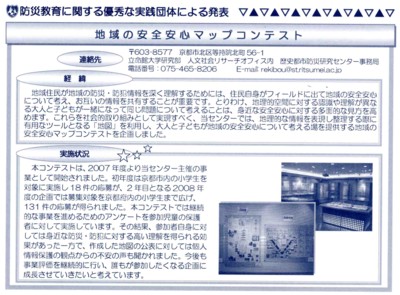
防災教育チャレンジプランhttp://www.bosai-study.net/index.html
伝統的建造物群保存地区に焦点をあてた文化遺産防災のシンポジウムが創思館カンファレンスルームにて行われた。まず、京都市消防局企画課長の山内博貴氏による「京都市における文化財防災対策について」と題する講演があり、京都の事例が紹介された。その後、立命館大学理工学部教授の大窪健之氏による南丹市美山町、立命館大学理工学部教授の山崎正史氏による近江八幡市八幡地区、篠山氏教育委員会の成田雅俊氏による篠山市篠山地区、米村博昭氏による橿原市今井地区の事例が紹介された。これらの地域では通常の生活が行われているためにそれに伴う問題もあり、文化遺産防災の難しさの課題が浮き彫りにされた。会場には、研究者や行政関係者、市民、学生など多くの参加があり、活発な質疑が行われた。
東本願寺では、2011年に宗祖親鸞聖人七百五十回忌をむかえるために、現在御影堂の修復工事を実施中であり、今年末の完成にむけて最終工程に入っている。今回の工事は、明治初期の再建以来の本格的なもので、屋根瓦の葺き替えや、内陣中柱の補強、屋根裏の補強などが中心である。この工事では、伝統的な工法を継承するだけでなく、随所に新しい技術や素材を用いている点が大きな特徴である。また屋根重量の軽減、柱の補強、床下のスプリンクラー設置など、地震対策、放火対策にも重点が置かれている。本年末には素屋根がはずされ、建設面積で世界最大の木造建造物が、姿をみせる予定である。御影堂修復工事現場の視察には、本学の歴史都市防災研究センターのメンバーなど17名が参加し、日頃目にすることのない屋根や小屋組の中を、専門家の説明を受けながらそれぞれ専門的な立場からみることができた。
文化遺産とその防災施設をみることを目的として、奈良の視察を行った。午前中に法隆寺で、昭和24年の火災で焼けた金堂の壁画の現状と防火設備について法隆寺の執事および奈良県教育委員会担当官より説明を受けた。午後からは、平城宮の大極殿復元作業現場を訪れ、奈良文化財研究所の担当者から復元作業および地下の免振装置などの説明があった。その後、奈良町に移動し、国宝の元興寺極楽坊の住職から寺の説明を受け、防災施設を見学した。この寺の周辺は、民家が密集していて、延焼の危険性をいかに軽減するかという課題があることがわかった。
